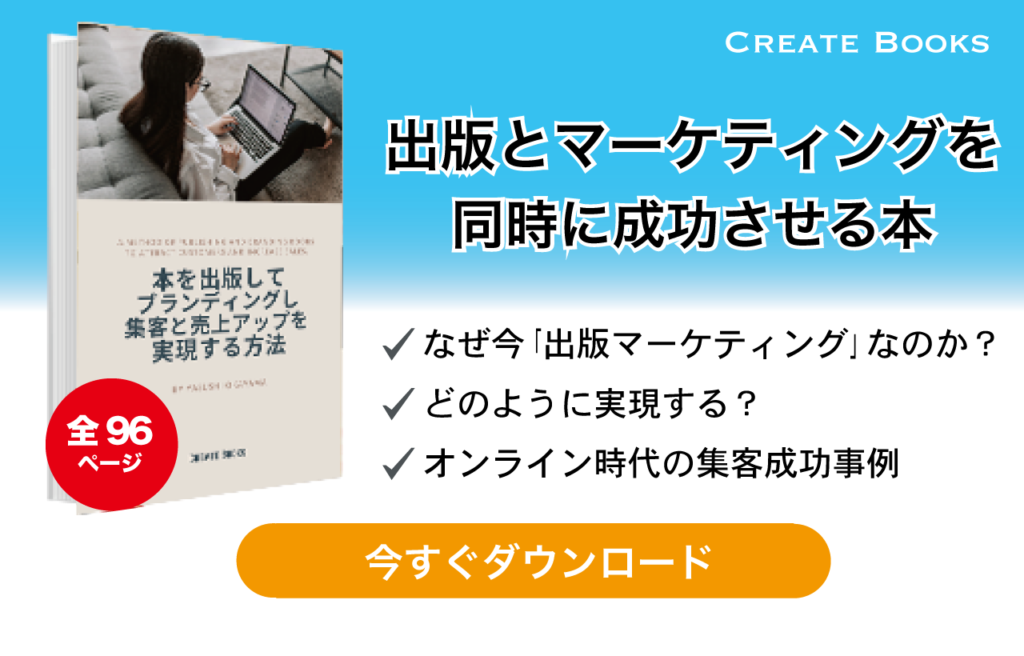【出版】編集者の役割と「本」の役割
2021/10/24
この記事は 0 いいね!されています。(以下はリニューアル後の数値です)
11月に入りましたね。
だいぶ肌寒くなってきましたが、いかがお過ごしですか?
風邪などひいていませんか?
1日に、明治神宮に行ってきました。
運良く豊穣祭をやっていて、三味線、尺八の演奏に巡りあったのです。

普段は静かな境内に、三味線の音色が響き渡ると 日本の文化の奥ゆかしさや慎み深さがしみじみと伝わってきました。
たくさんの奉納物、餅、酒、特産品、とともに
歌や踊り、音楽も神前に奉納されるのです。

立派な鏡餅がずらりと並べられて、まるでお地蔵さんのよう! この後の餅の行方が気になります(笑)
長らく工事中だった南側の門も改修が終わり、
午前中の雨も上がったせいで
普段以上に穢れなく、さわやかな空気が漂う境内に
伝統の音色が響き渡ると、
秋の実りの喜びとともに、自然と感謝の念が沸いてきます。

清々しい空気感が漂い、木々の香りとやわらかな斜光線とともに 訪れるすべての人をやさしく包んでくれます。
「ありがたいなー」
「生かされてるなー」
「今日もまた祝福がたくさんあって、なんて恵まれているんだろう!」
僕は神前でお一人お一人の著者さんの顔を思い浮かべながら、
きちんと本ができることと、
その本が広く読者の手元に届き、
著者の思いが広がっていくことを
しっかりお願いしてきたのです。
●困ったときこそ「編集者」に頼ろう
著者さんのなかには
「自分の本が売れるイメージができない」
という方がときどきいらっしゃいます。
きちんと企画書ができて、
文章も仕上がりつつあるというのに、
なぜか自信がないご様子。
そんなときは、実は別のところに不安や心配のタネがあるものです。
それがちょうど出版準備と重なって、
自分と向き合わざるを得ない状況なので、
その「不安や心配のタネ」=「人生の課題」が
改めて浮き彫りになることが往々にして起こります。
すると目の前に抱えている「本を出す」という課題に対して
ネガティブな感情が引き起こされます。
「こんな本を出して意味があるんだろうか」
「出してもどうせ売れないに違いない」
「批判がきたらどうしよう……」
「どうせ○○さんの二番煎じと言われるだろうし、意味ないんじゃないの?」
そんなさまざまな怖れや無価値感が渦巻いてきます。
特に書けないときに、筆が進まないときに、
こんな不安や不満のタネがむくむくと芽を出してくるのです。
そんなときは、遠慮なく「担当編集者」に相談するのが一番です。
ただ話をして、自分の気持ち(不安や不満)を正直に伝えるだけで、
だいぶ氣が収まるもの。
時間があれば「担当編集者」をお茶に誘っても良いでしょうし、
Skypeで30分話すだけでも、
自分を取り巻く空気ががらっと変わったりします。
著者の気持ちに寄り添って、ときには読者の立場になって、
編集者は著者のことを良く観ています。
自分のことは意外と自分では観れないもの。
文章執筆のサポートだけが編集者の仕事ではありません。
執筆のための準備(=心持ち、マインドセット)についても
編集者は教えてくれるでしょうから、
一度ハラを割って「担当編集者」に話をしてみてはいかがでしょうか。
●著者の想いを伝える「本」の役割
前にもこのブログ記事で書きましたが、
「本は波動商品である」とある作家さんが言っていました。
その心は、著者の「想い」が言外にあるものも含めて
「本」という物理的な存在に宿る(移る)ので、
読む、読まないに関わらず、
「伝わるもの」があるというのです。
(これは僕なりの理解ですが!)
よく「行間を読め」と言いますが、実はこの
「言外に伝えるもの」を本から汲み取ることも指しているのです。
それは、ひと言でいえば「著者の想い」。
心理学用語でいえば「潜在意識」であり、
さらに「集合的無意識」(byユング)にもつながる話なのです。
実は、人は「非言語領域」のコミュニケーションの方が強く影響されます。
アメリカの心理学者アルバート・メラビアンによると、
態度や感情のコミュニケーションにおいて、影響を及ぼすのは話の内容などの言語情報が7%、口調や話の早さなどの聴覚情報が38%、見た目などの視覚情報が55%の割合である。(「メラビアンの法則」より)
つまり9割以上は非言語コミュンケーションなのです。
物理的な存在である「本」も、実はこの非言語領域で伝わるものがあります。
それは、表紙のデザイン、色、活字の書体、本の重さ、大きさや厚み、
あるいはインクのにおいなどのほか、
五感で感じ取れないもの、五感以外で感じ取っているもの
(それは電気的なこと、磁気かもしれないし、エネルギーかもしれません)
が乗ってくるのです。
だから著者は、自分の本に、自分が書く原稿に
「どんな思いを乗せるか」を、慎重に考えましょう。
本を「売る」ことはもちろん大切ですが、
単に「売れるかどうか」だけを考えていては、読者に見抜かれてしまいます。
どれだけの思いがあって本を創ったのか(創っているのか)。
それは、読む人すべてを幸せな笑顔に導くものなのか。
そして、その結果どうなってほしいのか。
そのことにきちんと自分なりの答え、
つまり「哲学」だったり「コンセプト」を持って
本作りを楽しんで下さい。
![岡山泰士[公式サイト] | クリエイト・ブックス](https://createbooks.jp/wp-content/uploads/f55c23db80b3ae439fed0685201b6ee1.png)